「心身の不調は自律神経の影響かもしれない」という言葉をよく耳にします。しかし、自律神経とは一体どのような神経なのでしょうか?簡単に言えば、自律神経は「内臓の働きを調整する神経」であり、全身の臓器と連携して身体の内部環境を維持しています。本記事では、自律神経に関する歴史的な研究を振り返りながら、交感神経や副交感神経の仕組み、さらには最近発見された「第三の自律神経」の役割についても詳しく解説していきます。
(*本記事は『自律神経の科学 「身体が整う」とはどういうことか』の抜粋および再編集版です。)
「快」と「不快」を感じるメカニズム
皆さんは、脳の中に「快」を感じる場所があることをご存知でしょうか?その場所は視床下部の外側部に位置しています。この部分に電極を埋め込み電流を流すと、ネズミはその刺激を求めて何度もスイッチを押すようになります。このことから、特定の部位が「快」を生み出すことがよくわかります。こうした「快」を感じるエリアは、一般に報酬系や快中枢と呼ばれています。
報酬系は、摂食、飲水、性行動などの本能的な欲求を引き起こす部分とも重なっており、本能が満たされることで幸せを感じるのです。
同じ視床下部には、「不快」を感じる場所も存在します。この部分は嫌悪系や懲罰系と呼ばれており、ネズミにおいてはこのエリアに電流が流されると、嫌悪感から逃避行動を示します。嫌悪系は「防衛部位」とも関連しているようです。
防衛部位が活性化することで、「防衛反応」や「闘争または逃走反応」が引き起こされることは先に触れました。このプロセスに大きく関与しているのが、オレキシン神経です。オレキシン神経は、オレキシンという神経伝達物質を含み、室傍核や中脳など広範囲に影響を与えることで、防衛反応時の自律神経反応を誘発しています。さらに、オレキシン神経がCRH神経を活性化することにより、自律神経や内分泌の反応を引き起こす可能性も示唆されています。
自律神経の活動と感情との関連
視床下部と並んで、大脳辺縁系は情動の発現に重要な役割を果たしています。大脳辺縁系が「情動脳」と呼ばれる理由は、感情に基づいた適切な行動が上位の大脳辺縁系から視床下部に指令されるためです。報酬系は視床下部のみならず、他の脳領域にも存在し、感情に応じた自律神経の活動を調整しています。
褒められることがもたらす快感
報酬系は、称賛を受けることで勉強へのやる気を引き起こす一方、薬物によっても刺激されます。コカインや大麻などの薬物が脳内の報酬系に作用するため、薬物依存症などの様々な依存症が生じるのです。
感情の中枢「扁桃体」
大脳辺縁系の中でも特に重要な役割を果たすのが扁桃体です。この部分は「恐れ」に深く関与しており、猫の場合は扁桃体が刺激されると防衛反応が誘発されます。また、人間においても、扁桃体の刺激は怒りや恐れを引き起こします。逆に、扁桃体が損傷すると恐怖感がなくなることがあり、その影響で危険を認知できなくなることもあります。
ヒトの情動行動の複雑さ
大脳辺縁系を介する情動行動は動物とヒトで大きく共通していますが、ヒトの場合は大脳新皮質の発達の影響でより複雑です。外部からの情報は扁桃体と大脳新皮質の両方に伝達され、それぞれの情報が相互に影響を与え合い、高次の情動が生み出されます。このプロセスによって、様々な自律神経反応が引き起こされるのです。
情動が私たちに与える影響は大きく、怒りを感じると心拍数が上がり、体温が上昇することがあります。一方、嫌悪を感じると心拍数や体温は低下するのです。これらの変化は、感情が視床下部に伝達されることで自律神経系に影響を及ぼし、内臓機能に変化をもたらす結果となります。
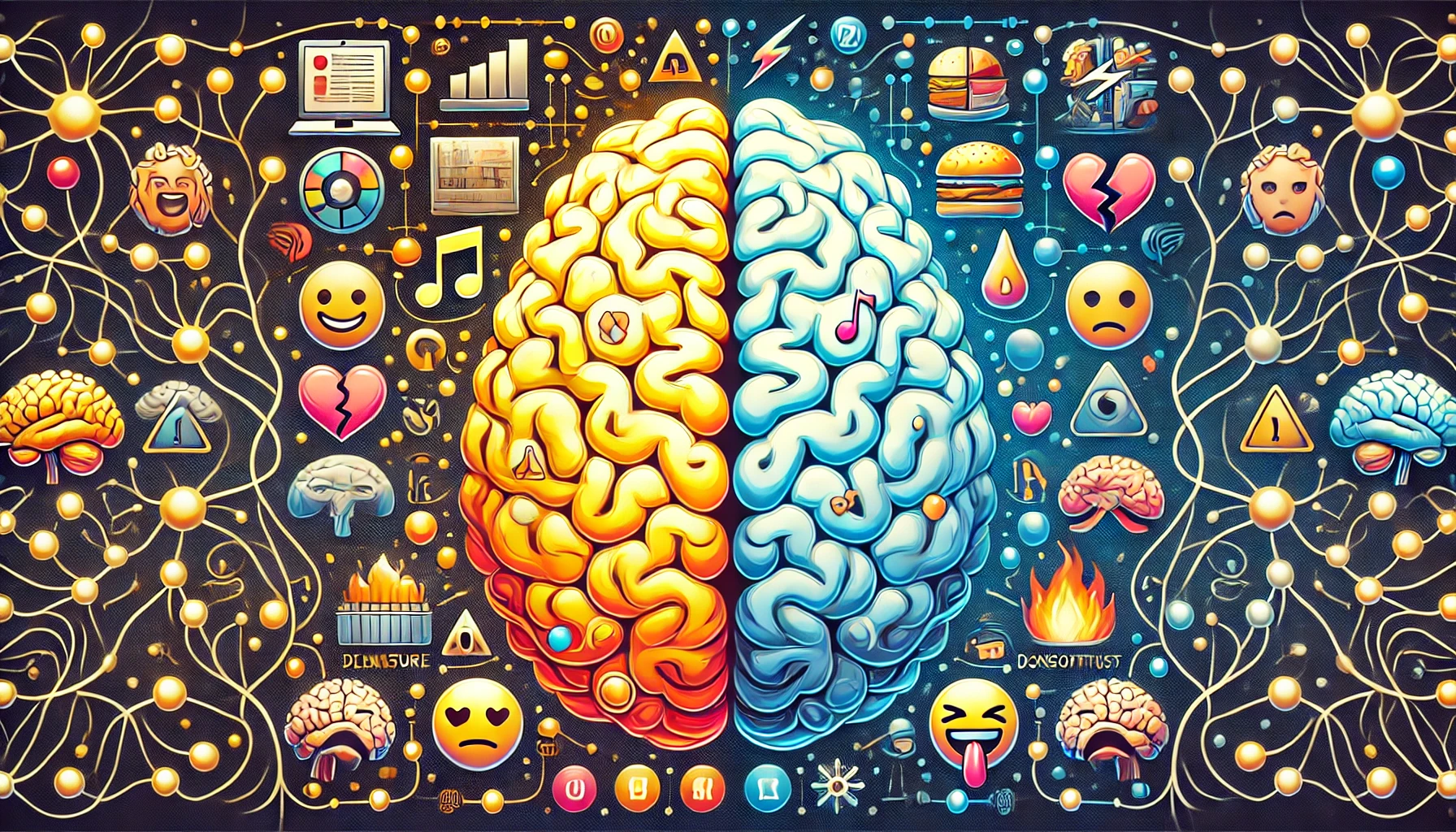

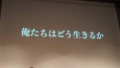
コメント